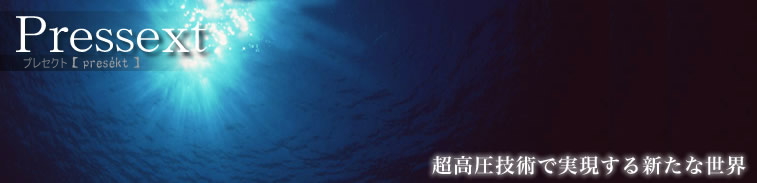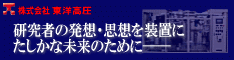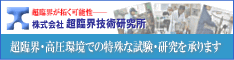食の安心、安全や健康志向が高まる中、地域の食材や技術を生かした新商品の開発が、地場の食品業界で活発化している。その支援機関として、酒どころ広島の醸造研究から始まった広島県立食品工業技術センター(広島市南区)の役割も重要性を増している。現場を追った。(永井友浩)
「通常は半年から2年かかる魚醤(ぎょしょう)がわずか1日でできる。今回の技術は、カキエキスや大豆栄養のサプリメントなど地元の食材を使った幅広い食品製造に応用できる」。流通保全技術部の岡崎尚部長(47)は力を込める。
開発したのは、圧力をかけてさまざまな食材をエキス状に変える加圧装置。温度を40~60度に保った装置に魚介類などの原料を入れ、深さ5千~1万メートルの深海に当たる高圧をかけると、酵素分解が早まり、液体になるのだ。
微生物が死滅するため、味などに影響する腐敗防止用の塩も不要になる画期的な技術である。大豆など植物性の原料も、酵素を加えて短時間で液状化できる。特許を取得し、実験用プラントの地元メーカーの東洋高圧(西区)に対し昨年末、特許の使用を認める契約を結んだ。今後、同社から市販装置として製造される予定で、研究成果が実用化段階に入る。
「行財政改革が進む中、センターにも県民の厳しい目が向けられている。実際に役立つ研究が求められている」と岡崎部長。それだけに今回の技術への期待は大きい。
開発は、広島特産のカキをむく打ち子の高齢化に悩むカキ養殖業者からの相談がきっかけだった。水深4万メートルに相当する超高圧ではカキの殻と身が分離することが知られており、より簡素な装置の開発に成功した。
地御前漁協(廿日市市)に1998年、試験納入した。しかしカキをむく機械としてはコスト面から実用化を断念。技術の応用として浮かんだのが、瀬戸内の小魚を生かせる魚醤である。食品業者からも魚醤を使ったアジア料理に人気が出ているとの情報があった。
センターは52(昭和27)年に設立。前身は酒醸造を研究する18(大正7)年設立の県工業試験場である。総合的に食品を研究する公設の機関は中国地方で唯一だ。守本京三所長(57)は「中小企業が多い食品メーカーにとって『駆け込み寺』である。同時に食の総合研究機関としての役割も重要」と気を引き締める。
新聞・雑誌等への掲載
加圧装置で食材を液状化
2006.02.01
2006/02/01 中国新聞朝刊