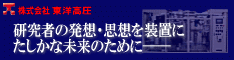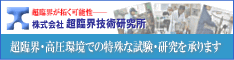広島駅から徒歩15分。閑静な住宅街に建つビルの1階から、突如大きな声が上がる。「オーライ、オーライ。そこでオーケーだ」。作業着姿の男性が、クレーンでつり上げた大きな円筒状の部品の移動を指示している。周囲を見ると、さほど広くない室内のあちこちに、大小様々な部品が雑然と置かれている。
何かの工場のように思えるが、いったい何を作っているのか。恐らく近所に住む人でも、それを知る人は少ないだろう。ここで作っているのは「超臨界装置」という極めて特殊な機械である。
超臨界装置は、水や二酸化炭素を超高圧、超高温にして、超臨界という特殊な状態を作り出す。超臨界の状態になった物質は、液体と気体の両方の性質を持ち、液体のように他の物質に容易に溶け込む一方、気体よりも拡散する性質が強い。
この変わった特徴を利用することで、例えば、アルカリ、酸などを使っても溶かすのが難しいダイオキシンを、超臨界状態の水と反応させて、その組成や濃度を測定できる。身近なところでは、花や食品から香りの成分だけを抽出して、エッセンスを作るのにも超臨界装置が使われている。
【研究者が苦手な仕事を代行】
利用するのは国や大学、企業の研究所といった限られた顧客だが、年間30~40台ほどの需要がある。その約半数を製造・販売し、シェア45%を誇るのが東洋高圧。社員わずか26人の中小企業である。
超臨界装置のような特殊な実験用機械の製造は、すべてが一品料理になる。ダイオキシンの測定にしろ、香り成分の抽出にしろ、実験の目的ごとに装置に求められる仕様と性能は大きく異なり、全く同じ装置というのはあり得ない。
しかも必要な仕様や性能を決められるのは、実験の内容を知っている研究者本人だけだ。装置の製造を委託する際には、「高温、高圧に耐える“釜”を製造するメーカーや制御装置のメーカーなどに、研究者が自ら詳しく仕様を説明しなければならない。これが研究者にとっては、ひどく苦痛のようだ」と野口賢二郎社長は言う。
超臨界装置について豊富な実績を持つ東洋高圧なら、簡単な説明を受けるだけで装置に求められる仕様を理解し、設計図を書いて研究者に示すことができる。
「研究こそが本業で、なるべく余計なことに時間を取られたくないと考える研究者は、装置を発注する際の手間が省けることを非常に喜ぶ」。超臨界装置の受注が好調な理由を、野口社長はこう分析している。
研究発表などの場を通じて、横のつながりが強い研究者同士のネットワークも、東洋高圧の高いシェアを支える理由の1つだ。研究成果を左右する実験装置を、どこに依頼して、どのように作ったかという情報は、学会や様々な会合を通じて研究者の間に口コミで広まる。
野口社長が、今や海外の研究者にまで名を知られる東洋高圧を創業したのは1974年。28歳の時だった。大学卒業後に勤務していた高圧バルブメーカーで、技術者として培った経験を生かし、カタログに載っていない一品料理の高圧バルブの製造を請け負うビジネスを思いついたのだ。
「カタログに載っている既製品のバルブは1個数千円。特注品ならその数倍に価格が跳ね上がる。サラリーマン時代に親しくなっていた金属加工メーカーに製造を委託すれば、大きなビジネスになると確信していた」
安定したサラリーマン生活を捨てて、起業することにも不安はなかった。野口社長は学生時代、大学を休学しヒッチハイクで世界53ヶ国を巡った経験を持つ。旅を続ける中で、町の商店主から大企業のオーナーまで様々な人と知り合い、いつかは自分の会社を持ちたいとの思いを強くした。
「たとえ規模は小さくても、自分の店や会社を持つ人が仕事にかける情熱に強く惹かれた」。大学卒業後、とりあえずメーカーに入社したのも、技術者としての経験を積み、それを将来に生かすためと割り切っていた。
そして入社から6年。大きな希望を抱き、会社を起こした野口社長だったが、当初は思うような成果を上げられなかった。
当時、広島の近くで、高圧バルブの特注品を必要とする顧客は、川崎重工業や三菱化学など、研究施設を持つ大手メーカーに限られていた。そこに28歳の若者が何のつてもなく飛び込み、研究者と面談を求めてバルブの注文を取ろうとしても、相手にされるはずがなかった。
【数ヶ月ねばって初受注】
状況が変わったのは、数ヶ月が過ぎた頃だ。ねばり強く複数の顧客企業との交渉を続けてきた野口社長の高圧バルブに対する知識の豊富さと熱意が評価され、小さな仕事を受注することに成功した。
野口社長は仕様書を受け取ると、その足で製造を委託する金属加工メーカーを訪れ、翌日の朝には自ら製品を届けて相手を驚かせた。「ビジネスで成功するのに、誠実さに勝るものはない」。放浪の旅で得た教訓は、若き企業経営者が初受注を獲得するための強力な武器となった。
その後、高圧バルブ専門から大型の化学実験装置へと扱い品目を増やしていき、70年代後半からは、超臨界装置の製造も請け負えるようになった。これも野口社長の誠実な仕事ぶりが認められたことが大きい。
野口社長は、受注案件が増えて仕事が忙しい時でも、化学や工学関係の学会誌や論文を読み、第一線の研究者に負けない知識を身につけようとしてきた。その一方で、製造する装置の品質や納期の管理も怠らなかった。
かつて超臨界装置を必要とするような企業は、ほとんどが自社で装置を作っていたが、野口社長の豊富な知識と仕事ぶりに信頼を寄せる研究者が東洋高圧の製品を使うことを望み、外注するケースが次第に増えていった。
現在、超臨界装置の受注は年間20件ほどで、その売り上げは約3億円。高圧ガスを使う化学実験装置などを含めた全社売上高は約8億円。経常利益は約1000万円で、不況下でも安定的に推移している。こうして押しも押されもせぬ超臨界試験装置のトップメーカーとしての足場を固めた現在でも、顧客からの信頼に応えようとする生真面目さは何ら変わらない。
例えば、東洋高圧では案件ごとに担当者を決めて、装置が完成するまでに要する約5ヶ月間、専従担当者として責任を持つ体制にしている。「装置の製造過程では、細かい仕様変更がよく起きる。これを着実に反映するには、最初から最後まで同じ人間が担当するのが望ましい」。常識的には設計・製造の工程ごとに担当者を置いた方が効率的だが、顧客からの評価が高い今の仕組みを変える気は全くない。
顧客重視の経営を地道に推し進める一方で、超臨界装置にさらに注力するため、売り上げ的には大きい化学実験装置などの事業を分社化することも検討している。世界を放浪し、若くして起業した大胆さと、顧客を何より大切にする慎重さ。相反する資質を併せ持つ野口社長は、その使い分け方を心得ているようだ。